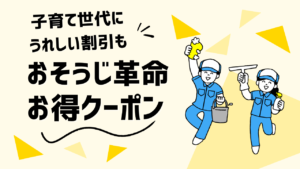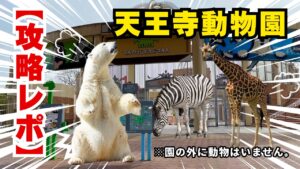産後ボロボロの身体で毎日赤ちゃんのお世話をしている皆さん、本当にお疲れさまです。
とくに初めての育児の場合、赤ちゃんのことが何から何まで分からなくて苦労する方も多いと思います。
核家族化が進んで、身近に頼れる先輩ママがいないことも多いですし、昔と今では育児の方法が異なっていることもあるので、ママが一人で悩んでしまうこともありますよね。
私自身も長女を出産したときに、赤ちゃんのことが何も分からなくて悩むことも多かったです。そこでX(SNS)でアカウントをつくり、月齢が近いママとよく悩みを相談しあっていました。Xのママたちは本当に心強くて今でも同志だと思っています(笑)
なかでも多くのママとパパが苦しむのが寝かしつけではないでしょうか?
赤ちゃんの寝かしつけで苦労したことのない親って世の中にいないのではないかとすら思います。
誰もが一度は「もう!なんで寝ないの!?」「早く寝てよ!」とさじを投げたくなったことがあるはず。
今これを読んでくださっているママやパパもきっとそうではないでしょうか。
私は少しでもママとパパが楽できるようになるには寝かしつけに役立つアイテムをどんどん使うべきだと思っています。
とはいえ、これだったら絶対に効果がある!というアイテムは残念ながら存在しません。
赤ちゃんが気に入ってくれるかどうかは使ってみなければ分からないのが正直なところです。
合う・合わないは赤ちゃん次第ではありますが、私自身も赤ちゃんの寝かしつけに悩みながらも本やネット、SNSを使って情報収集をしていろんなアイテムを使ってきたので、それらを紹介したいと思います!
今回ご紹介するアイテムで赤ちゃんが寝てくれて、ママとパパの睡眠時間が少しでも確保できることを願っています……!
寝かしつけで重宝しまくったアイテム12選


赤ちゃんの寝かしつけで重宝したのが以下のアイテムたちです。
- ハイローチェア
- バウンサー
- 抱っこ紐
- スワドル
- 授乳クッションとクッションを組み合わせる
- 魔法のラトル
- おやすみたまご
- 胎内音が流れるぬいぐるみ
- テテオおしゃぶり入眠ナビ
- ベビーアロマ
- LaLaCo(反力発生チェア)
- おやすみシアター
これらのアイテムについて詳しくみていきましょう!
なかでも私が勝手に寝かしつけ三種の神器と呼んでいるのは、①ハイローチェア、②バウンサー、③抱っこ紐の3つです。
ハイローチェアとバウンサーは主に日中の寝かしつけに使うことが多かったですが、乗せるとすぐに寝てくれたのでとても助かりました。
1 ハイローチェア
ハイローチェアに乗せてゆらゆらと揺らせば寝てくれる赤ちゃんが多いと思います。
電動タイプのものだと自分で揺らす必要がないので「ちょっと家事をしたい!」というときにも便利です。
ただお値段が張るのが悩みどころ。
わが家は手動のタイプを使いましたが、少し揺らせばすぐに赤ちゃんが寝てくれたので、「揺らし続けなければならない」ということはありませんでした。
赤ちゃんが寝てくれている間に食事をとったり、ちょっと家事をしたりできましたよ。
2 バウンサー
新生児の時ではないのですが、生後4〜5ヶ月に導入したのがベビービョルンのバウンサーでした。
赤ちゃんが自分でバウンサーを揺らして遊んだりするのに良いかなと思って導入したのですが、ゆらゆら揺らして遊んでいるのかと思っていたら、赤ちゃんが知らぬ間に寝ている!!なんてことがしょっちゅうありました(笑)
赤ちゃんが遊んでいる間に食事をとりたい、ちょっと家事をしたいという時にも役立つと思います。
3 抱っこ紐
抱っこ紐は種類が多くて選ぶのが難しいですよね。
「よく寝る!」とオススメされているのはコニーの抱っこ紐。
生後2週間から使えるのも嬉しいポイントです。寝かしつけ用にひとつあっても良いと思います。
4 スワドル
スワドルは日中というよりは夜間に使っていましたが、娘も息子もぴったりハマっていましたね。
腕はWの形、脚はM字になるように(固定されない)なっていること、伸縮性があって体を動かせるものを選ぶとよいと思います。
私は奇跡のおくるみの正規品として販売されているスワドルアップを使っていました。
友人の出産祝いにも「寝かしつけにいいよ!」とプレゼントしたほどです。
5 授乳クッション+クッション
日中だけですがクッションと授乳クッションを重ねるように置いて、その上に赤ちゃんを寝かせていました。
赤ちゃんはお母さんのお腹の中で丸まって過ごしていたので、平らな場所に置くよりも丸まった置き方の方が寝てくれたりします。
授乳クッションを駆使しながらまんまるに寝かせるとよく寝てくれました。
6 魔法のラトル
この魔法のラトルには何度助けられたか分かりません。
自宅で赤ちゃんがギャン泣きしているときはもちろん、外出先でもよく使っていました。
ラトルを振ることで、赤ちゃんが眠るわけではないのですが、泣き止んでくれたので私自身の精神が安定しました。
1,000円程度で購入できる商品なので、ひとつ手元に置いてみて損はないと思います。
2歳の娘はこの魔法のラトルをマイク代わりにして、歌をうたって遊んでいます。どれだけコスパの高いおもちゃなんだ…!
7 おやすみたまご
抱っこしているときは寝ているのに赤ちゃんを置くと泣いてしまう背中スイッチ。
その背中スイッチを発動させることなく寝かしつけが可能になるのがおやすみたまごです。
授乳クッション代わりにもなるので便利です!
8 胎内音が流れるアイテム
いろんなメロディや胎内音が流れるアイテムもあります。
ホワイトノイズの音は赤ちゃんが落ち着くともいわれていますよね。
手軽に取り入れられるのでオススメです。
9 テテオおしゃぶり入眠ナビ
おしゃぶりがないと寝られないという赤ちゃんもいますよね。
息子はあまりおしゃぶりは好きではなかったのですが、娘はねんね期におしゃぶりをよく使って寝かしつけをしていました。
コンビからは入眠に適したおしゃぶりも販売されているのでおすすめです。
ただデメリットもあるといわれているので、おしゃぶりをやめるタイミングも考えてくださいね。
10 ベビーアロマ
赤ちゃんにとって毎日のルーティンってありますよね。
その中で取り入れたいのが香り。
リラックスできるアロマは赤ちゃんだけでなくママの心もほぐしてくれます。
11 LaLaCo(反力発生チェア)
赤ちゃんが寝るまでの間ずっと立ち抱っこでゆらゆらするのって大変ですよね。
私は疲れるとソファやベッドに座って座りながらゆさゆさと揺らしていたのですが、これって何かいいアイテムないのかしら?と思って見つけたのがLaLaCoという椅子でした。
多くは子どもの姿勢矯正のための椅子として使われていることが多いようですが、座り抱っこでの寝かしつけにも使われています。
バネが適度に反発してくれます。縦のゆらゆらで寝かしつけている方にとくにオススメです。
12 おやすみシアター
リラックスさせてくれるやさしい音楽と星座を映し出すディスクが入っています。
産後すぐには使えないかもしれませんが、赤ちゃんの視力が上がってきたら導入してはいかがでしょうか
。毎日の寝かしつけのルーティンにしても良いですし、寝る前のリラックスタイムとして親子で楽しんでもよいと思います。
赤ちゃんが泣き止む音楽を聴かせてみる
音楽を流すと赤ちゃんが泣き止むと聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
赤ちゃんの泣き止む(といわれている)音楽をご紹介します。
効果の有無は赤ちゃん次第なのでぜひ一度試してみてください。
1 POISON(反町隆史)
赤ちゃんが泣き止む曲のテッパンといえば反町隆史さんのPOISONですよね。
ただうちの子どもたちにはまったく効果がありませんでした。
全然泣き止まないので、赤ちゃんの泣き声が響き渡るなか私がPOISONを聴くだけ…という状況になりました。
歌詞も2番までバッチリ覚えてしまいました(笑)
2 タケモトピアノ
「みんなまーるくタケモトピアノ」は、誰もが一度は口ずさんだことのあるCMではないでしょうか。
この曲は息子には効果があり、一時的ではありましたが泣き止んでくれました。
3 般若心経
これは試した方は少ないと思います。
お経って大人が聴いていても眠たくなってしまうので、赤ちゃんに聴かせたら寝てくれるのは?と思い聴かせてみたのですが、それがドンピシャで泣き止んで寝てくれました。
ただ、部屋を暗くして般若心経を流すので、正直少し怖いです。
4 ドライヤー音
胎内音や川のせせらぎ、ビニールの音など泣き止み音っていくつもありますよね。
YouTubeやママ向けアプリに音源があることもあります。
なかでも娘と息子に効いたのがドライヤー音でした。
とくにお風呂上がりにドライヤーをするとより効果的で、ドライヤーをしている間に寝てしまっている……ということもありました。
まとめ
赤ちゃんの寝かしつけで重宝したアイテムは以下の12個でした。
- ハイローチェア
- バウンサー
- 抱っこ紐
- スワドル
- 授乳クッションとクッションを組み合わせる
- 魔法のラトル
- おやすみたまご
- 胎内音が流れるぬいぐるみ
- テテオおしゃぶり入眠ナビ
- ベビーアロマ
- LaLaCo(反力発生チェア)
- おやすみシアター
試せそうなアイテムはありましたか?
赤ちゃんはよく寝る子もいれば、全然寝てくれない子もいて、苦労しているママとパパも多いと思います。
わが家は娘も息子もわりと寝てくれるタイプの赤ちゃんだったと思いますが、それでもとても苦労しました。
今回は寝かしつけに関するさまざまなアイテムをご紹介してきましたが、お子さんによって合う合わないがありますので、試せそうなものをひとつでも試していただき、少しでも効果があれば幸いです。